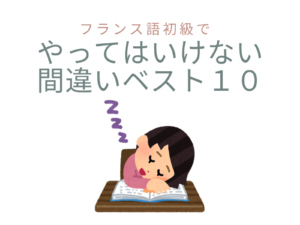© たじまのフランス語 All rights reserved.
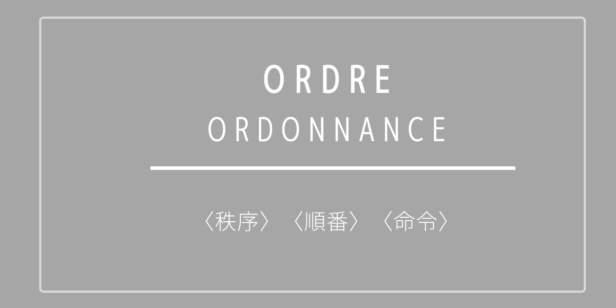
【名詞】「ordre」「ordonnance」を使いこなす!【中級〜上級】

【名詞】「ordre」「ordonnance」を使いこなす!【中級〜上級】
ボンジュール、たじまです。
みなさん、名詞の「ordre」と「ordonnance」の使い分け、しっかりできていますか? そして動詞の「ordonner」もありますね。この記事では、これらの言葉のネットワークを整理しておきましょう。
接頭辞「ord」の意味するところ
まず動詞の「ordonner」を見てください。このなかには「donner」が入っていますが、語源的にはそれほど関係がありません。むしろ関係があるのは、「ordinaire(いつもの)」というような言葉です。この接頭辞「ord」は、〈配列〉そして〈秩序〉の意味をもっています。つまり〈きれいに並んでいること〉それが、「ordre」のコア・イメージです。
仏仏辞典にはこんなふうに定義されています。
Ordre=arrangement régulier des éléments d’un ensemble les uns par rapport aux autres (いろいろなものがきっちり並んでいて、ひとつになっていること)
つまり「いろいろなもの(éléments)」が「un ensemble(ひとつ)」になっているというのが、とても重要なポイントなのですね。すぐに思いつくのは、幼稚園や小学校の子供たちでしょうか。休み時間=自由時間は、好き勝手に、縦横無尽に走り回りますが、授業時間などでは、しっかり並ばなければなりません。学校はまさに「秩序(ordre)」とは何たるかを習う場所なのですね。
Tout est rentré dans l’ordre.(ぜんぶが元どおりに戻った)
このように、最初の状態が〈秩序〉であれば(たとえば機械の調子など)、そこから「元どおり」のような意味も当然、出てきます。
しかし機械とはちがって、人間はしばしば自分の力だけでは「秩序」に戻ることはできません。誰かに「命令」してもらわないと、無秩序のままだったりします。さきほどの子供たちがいい例かもしれませんが。ここから動詞「ordonner」には〈秩序をつくる〉→〈命令する〉という意味の広がりが生まれます。
そしてここから、〈命令〉をコアにした名詞「ordonnance」が生まれます。つまり、ざっくりいって、〈秩序〉をコアにした名詞が「ordre」であるのに対し、〈命令〉をコアにした名詞が「ordonnance」であるということですね。それを橋渡しするのが、「ordonner」という動詞です。
ちなみに「-ance」という接尾語は大きくふたつの意味があって、ひとつは「行為やその結果」を表すというもの(もうひとつは「性質や状態」です)。ここれは単純に、「命令する」という動作を名詞化するために、この「-ance」という接尾語が付け加わっているということです。
ordreを使いこなす!(1)――par ordre
「いろいろなもの(éléments)」が「un ensemble(ひとつ)」になっているというのが、名詞「ordre」の重要なポイントでした。しかし、そのような抽象的な言葉は、日本語にありませんから、このようなイメージを念頭に、状況や文脈に応じて、適切な日本語を考える必要があります。
On va faire par ordre.(順番にやろう)
日本語の「秩序」という言葉はかなり抽象度が高いので、現実的に何かを並べたりするときには「順」という言葉になります。この「par ordre」は、後ろに形容詞(句)をつけて「〜順に」という副詞句をつくります。
Vous pouvez ranger ces documents par ordre alphabétique ?
(この資料、アルファベット順に並べてもらえますか?)
Les demandes doivent être numérotées par ordre de priorité de 1 à 10.
(リクエストを優先度の高いほうから順に1〜10の番号をふらなければなりません)
Tu sais classer les nombres par ordre décroissant ?
(数を大きい順から〔=小さくなっていく順で〕並べられるかな?)
その他、「大事な順に」であれば「par ordre d’importance」、「好きな順に」であれば「par ordre de préférence」、「背の高い順に」であれば「par ordre de grandeur」となります。ただし、疑問文のときには、「par quel ordre」とは言わず、「Dans quel ordre」というフレーズになります。
Dans quel ordre se sont produits ces événements?
(どんな順番で起こったのですか、これらの出来事は?)
ordreを使いこなす!(2)――en ordre
フランス語で「片付ける(ranger)」「整理する(classer)」「整える(organiser)」「並べる(disposer)」は、少し曖昧になりはしますが、「mettre en (bon) ordre」という表現であらわすことができます。「片付いている」は「être en (bon) ordre」です。
このように「en」をともなって使われることが結構あります。
Les livres sont en ordre sur les rayons.
(本がきれいに平積みされている)
「mise en ordre」は「整頓」という意味合い。
C’est un exercice de mise en ordre.
(これは整理整頓の練習です)
ordreを使いこなす!(3)――定冠詞つきのl’ordre
このようにordreは、結構「無冠詞」で使われることが多いのですが、一方で抽象的な意味合いで使われるときには、定冠詞がついて「l’ordre」となることが多いですね。たとえば、冒頭の
Tout est rentré dans l’ordre.(ぜんぶが元どおりに戻った)
の「le」が示しているのは、「元の(秩序)」という限定された意味合いです。このほかにもたとえば、
A 100 ans, on sait que la mort est dans l’ordre des choses.
(100歳ですからね、亡くなられるのは当然だと思いますよ)
のように、自然の理・当然のこと、という意味合いで使われるときには「l’ordre」としてまちがいなく、定冠詞つきになります。
Il n’est donc plus nécessaire depuis le nouveau Code que l’ordre de la loi soit transmis par une autorité légitime.(だから新法ではもう必要なくなるんですよ、法的命令が法務当局から伝えられることは)
社会的・法的な意味での「l’ordre」は、いろいろあっては困りますよね。〈ひとつ〉しかないものについては、「le」で限定がつきますから、このようなケースでも当然、定冠詞がつきます。大きくわければ、このような「定冠詞つきのordre」と、無冠詞の「par ordre」や「en ordre」があるというのが、この名詞の基本です。
ordonnanceを使いこなす(1)――まずは「処方箋」
動詞「ordonner」のコア・イメージは、〈秩序(ordre)を与える(donner)こと〉。そこから生まれた「命令」が、「ordonnance」です。〈こうしてくださいね〉というイメージが、コアにあるわけです。
しかし日常的にいえば、人に命令されることは多くありません。役所からの呼び出しには「convocation」を使いますので、日常生活で最も使う「une ordonnance (médicale)」は、医者から処方される「処方箋」のことでしょう。〈この薬を飲んでくださいね〉ということです。
行政レベルでは「ordonnance」というと、もともと国王の勅令一般をいう言葉でした。国家が法によって命じる「une ordonnance」は、「行政命令(Ordonnance en droit constitutionnel)」です。刑法に基づく命令であれば、「〈こうしてください〉という刑罰ordonnance pénale」です。
王国であれば、命令の主体が変わって、日本語では「王令」となります。フランスの歴史に詳しくないと、何のことかわかりませんが、「Grande Ordonnance」といえば、1357年の「大勅令」のことです。
現在では、オルドナンスといえば、1958年の改正により、第5共和国憲法上の制度に基づく措置のことを示します。国民の信任を得て選ばれた議員たちが構成する議会の承認を得て発する政令のうち、通常は法律の領域に属する措置を、限定された期間に限り政府が発令することを許すものをこう呼びます。
小難しい話をしてしまいましたが、基本的には「ordonnance」は〈こうしてくださいね〉ということです。だから、意味的には「秩序・順番」を表すものであっても、場合によっては(ordreではなく)「ordonnance」を使うことができます。
たとえば、「les règles d’ordonnance d’un repas」といえば、食事を出す順番=秩序のルールのこと。最初にポタージュを出して、そのあとに魚か肉を出して、最後にデザートを出す、みたいなことですね。
「l’ordonnance des mots dans une phrase」といえば、文章のなかの言葉の秩序=配列のこと。これも、ルールによる外圧が少しはたらいている感じでしょうか。とにかく、「ordonnance」というのは、従うべきルールが大前提としてあり、それにちゃんとしたがってね、ということです。
まとめ
みなさん、フランス語の名詞「ordre」と「ordonnance」の用法のポイントは、つかめましたでしょうか? 「par ordre」「en ordre」は、日常的にも頻出の熟語的表現なので、どんどん使っていきましょう。